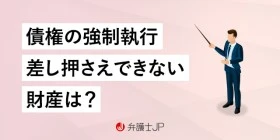- (更新:2023年05月26日)
- 債権回収
債権回収における強制執行の種類と必要となる書類・手続きとは?
友人にお金を貸したのに返してくれない、取引先に商品を納品したのに代金を支払ってくれないなど、そういったときには支払督促や民事裁判に訴えることもあります。それでもなお、返金や支払いが実現しないときに使える債権回収の手段が「強制執行」です。
強制執行はどのような種類があるのか、必要な書類や手続きとあわせて見ていきましょう。
1. 強制執行の種類について
強制執行とは、相手がお金を返してくれないときもしくは支払ってもらえないときなどに(このような義務を果たさないことを、「債務を履行しない」と表現することがあります)、国家機関(裁判所)が債権者に代わって強制的に相手に支払いや返金、明け渡しなどをさせる手続きのことです。
強制執行手続きは、着目するポイントによって種類の分け方が異なります。ここでは強制執行の方法に着目し、その具体的な内容について見ていきましょう。
(1)直接強制
強制執行の方法に着目すると、強制執行は「直接強制」「代替執行」「間接強制」の3つに分けられます。
直接強制とは、債務者の意思に関係なく、国家機関(裁判所)が直接かつ強制的に債権内容を実現する強制執行の方法です。
直接強制の例としては、執行裁判所が不動産を競売にかけてその代金を債権者に配る「不動産執行」や、給与や預貯金口座、売掛金、賃金などを差し押さえ、その中から債権者への支払いにあてる「債権執行」、商品や機械類などを差し押さえる「動産執行」などの金銭執行があげられます。
また、不動産執行には、不動産を競売にかけてその代金を債権者に配る「強制競売」と、不動産を管理して賃料などの収益から回収する「強制管理」の2種類の方法があります。
(2)代替執行
代替執行とは、債権者が第三者に債権内容を実現させて、その費用を債務者が支払うよう、国家機関(裁判所)が命じる方法です。
たとえば、土地の借主が地代を支払わなければ債権者が借地契約を解除するので、借主はその上の建物を取り壊して更地にして返さなければなりません。そのときに代替執行をすれば、第三者である業者に取り壊しをさせることができます。
そして、その際にかかった費用を債務者が支払うよう、国家機関(裁判所)が命じます。
(3)間接強制
間接強制とは、債務を履行しない債務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別の義務を課すことを警告(決定)することで、債務者に心理的圧迫を加えて、債務者の自発的な履行を促すものです。
たとえば、離婚後に養育費を支払わない男性に対し、養育費の支払期限までに支払い義務を果たさない場合、支払い完了まで1日あたり5000円を支払うよう裁判所が命じた判断があります(横浜家裁平成19年9月3日決定)。
(4)強制執行できない財産もある
ただし、債務者がいくら債務を履行しないとはいえ、強制執行できない財産もあります。強制執行のうち、現金や商品、機械類、絵画、ブランドバッグ、高級腕時計などが差し押さえの対象となる「動産執行」ですが、生活に不可欠な家財道具や衣類などについては差し押さえすることができません。
また、動産執行では現金を差し押さえられると前記しましたが、債務者の最低限の生活を守る目的で66万円までの金銭は差し押さえの対象外となります。債権執行をする際も、債務者の生活費を保障するために原則として給与額の4分の1相当までと規制されています。
また、年金についても強制執行は許されていません。ただし、養育費の回収が目的である場合は、給与額の2分の1相当まで差し押さえが可能です。
2. 強制執行の際に必要となるものは?
強制執行をするときには、債務名義・執行文・送達証明書の3つが必要になるので、それぞれ取得するための手続きを行います。また、相手方の財産状況に不安がある場合は事前に調査や仮差し押さえをすることも検討すべきでしょう。
(1)費用倒れを防ぐための財産調査と仮差し押さえ
費用をかけて強制執行をしようとしても、相手方に債務を履行できる十分な財産がなければ、費用倒れになってしまいます。そのために、まずは相手方に財産があるかどうかの調査をしたり、仮差し押さえしたりすることが必要です。
①財産調査
債権者の数や相手方の持っている財産について調査を行います。財産調査は簡単ではありませんが、弁護士に依頼すれば弁護士会を通じて銀行などに照会をしてもらえるので、何らかの手掛かりがつかめるかもしれません。
財産調査をしても相手にどれくらい財産があるのかがわからない場合は、必要に応じて裁判所に対して財産開示請求の手続きをするとよいでしょう。
②仮差し押さえ
債務名義を取得していない場合は、強制執行前に勝手に財産を処分されないよう、裁判所に仮差し押さえの申し立てをするのも有効です。ただし、申し立ての際には仮差し押さえをしてほしい債権が存在すること、仮差し押さえが必要なことの資料などの提出が必要です。
(2)債務名義
実際に強制執行をするには、債務名義が必要です。債務名義とは債権者と債務者、債権の存在やその範囲などを公的に証明する文書のことで、判決や調停調書、和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書などがこれにあたります。債務名義は正本が必要になるので、手元にない場合は作成に携わった裁判所や公証人に相談しましょう。
(3)執行文
次に、債務名義を出した裁判所に対して、執行文付与の申し立てを行います。執行文付与とは、債務名義に強制執行をすることができる効力を持たせるための手続きのことです。
(4)送達証明書
強制執行の際には、債務者に債務名義を送付することが必要ですが、きちんと相手方に送ったことを示すための送達証明書が必要です。公正証書の場合は公証役場で、その他の債務名義ではその判決や調書などが交付された裁判所で証明書を発行してもらいます。
強制執行の手続きは裁判所を介するものであり、自力で行うのは難しいため、強制執行を検討される際は弁護士に相談されることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

債権回収に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2022年05月23日
- 債権回収
-
- 2021年11月26日
- 債権回収
-
- 2021年11月19日
- 債権回収